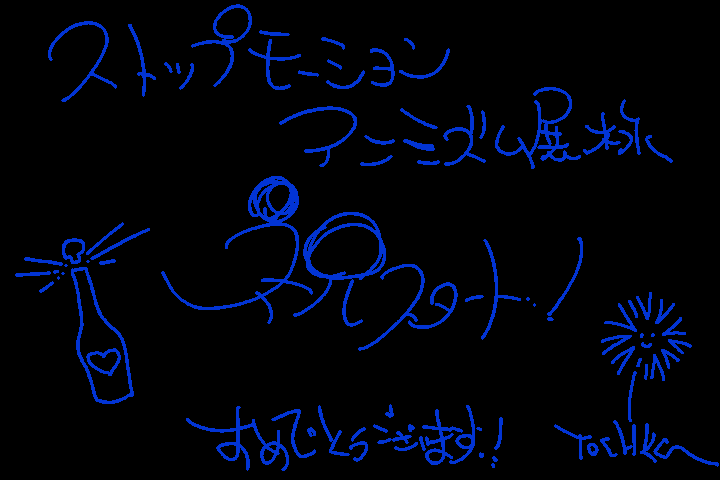本展にさいして、プランニングディレクターの阿部芳久様、横浜美術館 主任学芸員の松永慎太郎様よりコメントを頂戴しました。心より感謝いたします。
阿部芳久(プランニングディレクター)
私は文化庁メディア芸術祭や学生CGコンテストに20数年間かかわってきました。応募作品や受賞作品だけでなく、リサーチ活動なども含めて毎年多くの作品を見続けてきましたが、その中で東京藝術大学大学院映像研究科ではいつも気になる作品を見つけることが出来ました。
コンテストの仕事をしていると賞の結果にかかわらず、若い作家達がどのように成長していくかを追いかけて見ていきたいものです。しかしながら現実的には追いかけきれるものではありません。今回の企画展では学生時代と現在の作品をあわせて紹介されるので、きっと作家の変化や成長を見ることが出来るでしょう。
また、この10年間はアニメーションや周辺環境も大きく変わりました。立体アニメーションに焦点を絞ることで、様々な変化が鮮明に見えてくるのではないかと期待しています。
松永慎太郎(横浜美術館 主任学芸員)
越境するアニメーション
平面上、あるいは立体空間に創出される、静止した光景。そこに少しずつ変化をつけながら静止画を撮りため、連続映写することによって、動く絵、あるいいは動く写真へと変換する。この「アニメーション」と呼ばれる手法は、「映画」の中の一ジャンルとみなされがちだが、パラパラアニメなどの例もあるように、原理的には映画の誕生よりはるか以前から試みられてきた。「絵を動かす」という欲求にもとづく原初の表現がアニメーションだとすれば、逆に映画をアニメーションの「子」と捉えることもできる。
アニメーションの特性として挙げられるのが、画面内の構成要素の数量、形、動きの調整(特に単純化による強調)の自在性、つまり表現の自由度の高さである。1920年代に興隆したアヴァンギャルド芸術運動において、多くの芸術家が映像を用いた実験を展開したが、彼らがより純粋で強度のある「形」と「動き」の表現を追求すればするほど、その手法はおのずとアニメーションへと向かっていった。
一方でアニメーションは、まさにその表現の自由度の高さと明解さゆえに、年少者にとっての娯楽や教育素材としても格好のメディアであった。そのため戦後長きにわたり、アニメーションというと、制作手法や形式上のカテゴライズとしてよりも前に、「子供向け」という需要上の区分で認知されがちな状況が続いた。しかしここ20年ほどのアニメーションをめぐる著しい情勢変化-たとえば「ジャパニメーション」という造語まで生まれた日本の商業アニメの世界的ブーム、それに対峙するかのような個人レベルでの様々なアニメーション表現の隆盛、それらに呼応した教育現場におけるアニメーション学科の設立やカリキュラムへの導入の急増など-が象徴するように、アニメーションはひとつの自立的な文化として、表現者・需要者双方から「再発見」され、ジャンルとしての成熟に向かいつつあるようにも見える。
紆余曲折を経ながら積み重ねられてきた、アニメーションという表現をめぐる様々な取り組み。そこに何らかの通底するものを見出そうとするなら、それはある既成の枠組み-すなわち「時間」であるとか、「空間」(視野)、あるいは「死」といった、現実世界ではいかんともしがたい絶対的な存在-を乗り越えようとする、「越境」の欲望ではないか。
越境の志向が表現者をアニメーションへと駆り立て、ときにアニメーションという手法自体をも解体して、名状しがたいハイブリッドな視覚世界へとなだれ込んでいく。そんな多様化したアニメーションの現在地点を眺めながら、ふと思い起こせば戦前のアヴァンギャルドシネマの多くもまた「映像にアニメーションを取り込んだ不分明な表現」というべきものであったことに気づく。「アート」という概念から捉えなおされつつある現代のアニメーションは、おのずとその表現を原点へと立ち戻らせているのかもしれない。